×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
お題「敗北者」を更新しました。
最後のひとつ、です!忘れていた訳ではないです……><;
それから、20周年企画ということで、毎日更新開始します!
こちらからどうぞ!
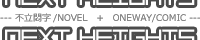
パスワードはふたりの誕生日(直高の順で8桁)を入力→OKボタンをクリックです!
そして今回のおまけは、私のキャンプ行きたい願望の表れです^^;
最後のひとつ、です!忘れていた訳ではないです……><;
それから、20周年企画ということで、毎日更新開始します!
こちらからどうぞ!
パスワードはふたりの誕生日(直高の順で8桁)を入力→OKボタンをクリックです!
そして今回のおまけは、私のキャンプ行きたい願望の表れです^^;
□つづき□
「キャンプ、ですか」
電話の向こうの高耶に、直江は聞き返した。
『そ。なんかこの前んとき、千秋のヤツが勝手に美弥と約束してたみたいで』
日帰りでキャンプ場まで遊びに行ったのが、ついこの間の話だ。
今度は泊まりで、ということらしい。
『ねーさんもまた来るみたいだし、おまえはどーするかと思って』
「そうですねぇ……」
実は照弘絡みの仕事の予定も入っていたし、どうしようかと悩んでいたら、
『………来たらきっと、楽しいぜ?』
高耶の遠慮がちな誘いに、直江の脳内スケジュールは瞬時に書き換えられた。
□ □ □
「トイレみた!?トイレ!穴しかあいてないわよ!」
「昔を思い出してみろよ?囲いがあるだけマシだろ」
「あああ……やなこと思い出しちゃった」
「米沢んときの、アレだろ」
「もー、いい加減忘れたいわ」
テントを組み立て終えた千秋と綾子がトイレ談義に花を咲かせている後ろの方で、
「そうそう、そうやってカドとっとくと形が崩れないわけ」
「へえ~、知らなかった」
「で、たまねぎも切り方によって味が変わってくるから。例えば──」
高耶が譲に包丁指南をしている。
さらにその隣では、直江と美弥がかまどに火を入れていた。
「ほら、楽に薪に火が移ったでしょう?」
「直江さんすご~~い♪」
美弥にキラキラとした眼で見つめられて、直江は困った顔をする。
「コツさえ知っていれば簡単なんですよ」
「そうそう。そのコツが掴めずに、昔どっかの誰かさんが苦労してたっけ」
千秋が横からチャチャを入れてきた。
「お前は米をといで来い、米を」
直江が飯ごうを差し出すと、
「おっし美弥ちゃん、一緒に行くか」
「はあい」
千秋は美弥を連れて水場へと消えた。
□ □ □
「まさか、ほんとにその恰好でくるとはね」
残った直江の元へ、綾子がやってくる。
さすがに上着は脱いでいたが、直江は今日もスーツだった。
千秋が言ったのだそうだ。
ポリシーなんだろ、だったら脱ぐんじゃねーと
「まあ、見慣れすぎて違和感ないけどねえ」
そう言いながら、綾子はちらりと直江の左手を見る。
「それ、外したって誰も気にしないわよ」
シャツの腕を捲った直江は、腕時計をつけたままだ。
直江も同じようにちらりと自分の左手首を見たあとで、
「していたって誰も気にしないだろう」
「まあ、ね」
綾子は首をすくめてそう答えた。
□ □ □
「こんな空気のうまいとこ来てまでタバコかよ」
声に驚いて振り返ると、高耶が立っていた。
「って、譲なら言うぜ」
夜空には数え切れないほどの星が光っている。
直江はそれらを眺めながら、優雅に一服中だったのだ。
「美弥さんは」
「ぐっすり。はしゃぎすぎて疲れたんだろ」
高耶は直江の吸いかけのタバコをとりあげると、口に銜えた。
「ガキの頃、よくキャンプごっこしてた」
注意しようと口を開きかけた直江は、いきなり始まった高耶の昔話を邪魔したくなくて口を噤んだ。
「美弥の友達が休みっていうとキャンプに行くから、自分も行きたいって言い出してさ。もちろん行けるわけねーじゃん?」
きっと、家庭内が荒れに荒れていた時期の話なのだろう。
「だから家で作ったカレー持って、公園行ってさ。レジャーシートでテント作って」
「楽しそうですね」
「いま思えばな。でも当時はみじめでしょうがなかった」
直江は灰の落ちかけたタバコを高耶の手から取り上げると、簡易灰皿の中へと突っ込んだ。
□ □ □
「美弥さんは幸せですね。いいお兄さんを持って」
「………どうかな」
高耶の胸の内に、罪悪感の霧が充満する。
「そう思ってもらえるよう、努力するしかないよな」
小さく呟いた。
それを聞いた直江は、
「私のコレは義務だと思ってやっていますけど」
と、自らの恰好を示す。
「あなたが美弥さんにしていることは義務からじゃない。愛情でしょう?」
直江の低く響く声が、周囲の森に溶け込んでいく。
「そこが、あなたの、あなたたる所以なんですよ」
「───……」
高耶は戸惑いながら答えた。
「オレのこと、よく知らないくせに」
まだ出会って二ヶ月やそこらなのだ、自分と直江は。
知った風に、語られたくない。
そう思うのに、心の片側ではまるで遠い昔からの知り合いのような気がしていた。
いや実際、そうなのだが。
「知っていますよ」
直江は高耶の方を見ながら言った。
「よく、知っています」
………そうかもしれなかった。
自分がこの男のことを誰よりも知っているような気がするのと同じで、この男も自分を誰よりも知っているのかもしれない。
満天の星の下、高耶は頬に男の視線を感じながら、そう考えていた。
電話の向こうの高耶に、直江は聞き返した。
『そ。なんかこの前んとき、千秋のヤツが勝手に美弥と約束してたみたいで』
日帰りでキャンプ場まで遊びに行ったのが、ついこの間の話だ。
今度は泊まりで、ということらしい。
『ねーさんもまた来るみたいだし、おまえはどーするかと思って』
「そうですねぇ……」
実は照弘絡みの仕事の予定も入っていたし、どうしようかと悩んでいたら、
『………来たらきっと、楽しいぜ?』
高耶の遠慮がちな誘いに、直江の脳内スケジュールは瞬時に書き換えられた。
□ □ □
「トイレみた!?トイレ!穴しかあいてないわよ!」
「昔を思い出してみろよ?囲いがあるだけマシだろ」
「あああ……やなこと思い出しちゃった」
「米沢んときの、アレだろ」
「もー、いい加減忘れたいわ」
テントを組み立て終えた千秋と綾子がトイレ談義に花を咲かせている後ろの方で、
「そうそう、そうやってカドとっとくと形が崩れないわけ」
「へえ~、知らなかった」
「で、たまねぎも切り方によって味が変わってくるから。例えば──」
高耶が譲に包丁指南をしている。
さらにその隣では、直江と美弥がかまどに火を入れていた。
「ほら、楽に薪に火が移ったでしょう?」
「直江さんすご~~い♪」
美弥にキラキラとした眼で見つめられて、直江は困った顔をする。
「コツさえ知っていれば簡単なんですよ」
「そうそう。そのコツが掴めずに、昔どっかの誰かさんが苦労してたっけ」
千秋が横からチャチャを入れてきた。
「お前は米をといで来い、米を」
直江が飯ごうを差し出すと、
「おっし美弥ちゃん、一緒に行くか」
「はあい」
千秋は美弥を連れて水場へと消えた。
□ □ □
「まさか、ほんとにその恰好でくるとはね」
残った直江の元へ、綾子がやってくる。
さすがに上着は脱いでいたが、直江は今日もスーツだった。
千秋が言ったのだそうだ。
ポリシーなんだろ、だったら脱ぐんじゃねーと
「まあ、見慣れすぎて違和感ないけどねえ」
そう言いながら、綾子はちらりと直江の左手を見る。
「それ、外したって誰も気にしないわよ」
シャツの腕を捲った直江は、腕時計をつけたままだ。
直江も同じようにちらりと自分の左手首を見たあとで、
「していたって誰も気にしないだろう」
「まあ、ね」
綾子は首をすくめてそう答えた。
□ □ □
「こんな空気のうまいとこ来てまでタバコかよ」
声に驚いて振り返ると、高耶が立っていた。
「って、譲なら言うぜ」
夜空には数え切れないほどの星が光っている。
直江はそれらを眺めながら、優雅に一服中だったのだ。
「美弥さんは」
「ぐっすり。はしゃぎすぎて疲れたんだろ」
高耶は直江の吸いかけのタバコをとりあげると、口に銜えた。
「ガキの頃、よくキャンプごっこしてた」
注意しようと口を開きかけた直江は、いきなり始まった高耶の昔話を邪魔したくなくて口を噤んだ。
「美弥の友達が休みっていうとキャンプに行くから、自分も行きたいって言い出してさ。もちろん行けるわけねーじゃん?」
きっと、家庭内が荒れに荒れていた時期の話なのだろう。
「だから家で作ったカレー持って、公園行ってさ。レジャーシートでテント作って」
「楽しそうですね」
「いま思えばな。でも当時はみじめでしょうがなかった」
直江は灰の落ちかけたタバコを高耶の手から取り上げると、簡易灰皿の中へと突っ込んだ。
□ □ □
「美弥さんは幸せですね。いいお兄さんを持って」
「………どうかな」
高耶の胸の内に、罪悪感の霧が充満する。
「そう思ってもらえるよう、努力するしかないよな」
小さく呟いた。
それを聞いた直江は、
「私のコレは義務だと思ってやっていますけど」
と、自らの恰好を示す。
「あなたが美弥さんにしていることは義務からじゃない。愛情でしょう?」
直江の低く響く声が、周囲の森に溶け込んでいく。
「そこが、あなたの、あなたたる所以なんですよ」
「───……」
高耶は戸惑いながら答えた。
「オレのこと、よく知らないくせに」
まだ出会って二ヶ月やそこらなのだ、自分と直江は。
知った風に、語られたくない。
そう思うのに、心の片側ではまるで遠い昔からの知り合いのような気がしていた。
いや実際、そうなのだが。
「知っていますよ」
直江は高耶の方を見ながら言った。
「よく、知っています」
………そうかもしれなかった。
自分がこの男のことを誰よりも知っているような気がするのと同じで、この男も自分を誰よりも知っているのかもしれない。
満天の星の下、高耶は頬に男の視線を感じながら、そう考えていた。

